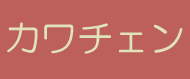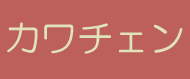�u����u�`�x�b�g�Ɠ��{�̌���j�@������̐��70�N�v�����O�A�쌳�r��������������������l����(�]�{�ÐL�j
�i�{�C�x���g�͏I���������܂����B���Q���������������X�A���肪�Ƃ��������܂����B�j
�@2015�N�āB�u���70�N�v�̐ߖڂɂ����邱�Ƃ��A�����m�푈�Ɠ��{�̔s��AGHQ�Ǘ����̂��̌�̕����̖͗l�Ȃǂ��e�[�}�ɁA���܂��܂Ȋp�x���猟���Ȃ���Ă��܂��B�������A�L�͂Ȍ���j�̂��ׂĂɖڂ��͂��Ă���킯�ł͂������܂���B���Ƃ��A���{�ƃ`�x�b�g�̏��a�̊W�j���A�قƂ�njڂ݂��邱�Ƃ̂Ȃ�1�y�[�W�ł��B
�@
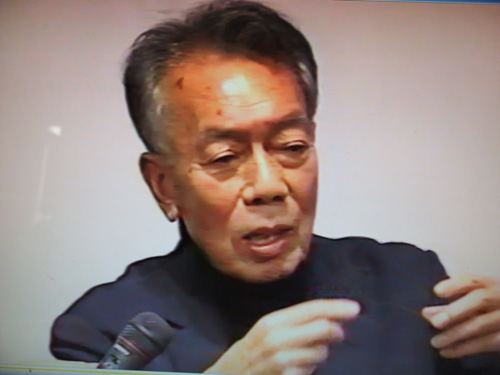 �@ �@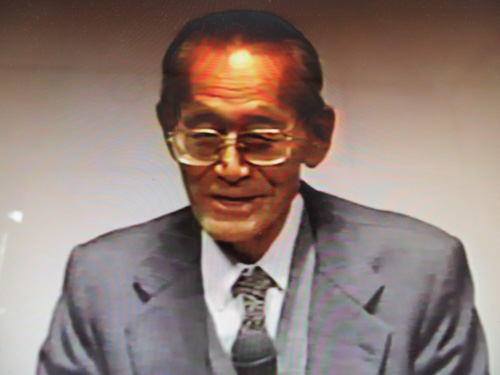
�@2015�N1���A�����m�푈��ڑO�Ƀ`�x�b�g�ɐ��������A�����Ă̔_�ƐN���̋��̎������ʼnƑ��Ɍ�����V�ɗ������܂����B�쌳�r���i�̂��ƁE�����j����B�i�ʐ^�E�j���N97�ˁB�����R�����@�փ����S���ꌤ�C���B���̒����w�`�x�b�g���s�@1939�x�ɁA�`�x�b�g�����̂������A�_���C�E���}14����4�˂̎��̃��T����̏�i�A�����̃`�x�b�g�̔_���̏�i�ȂNjM�d�ȑ̌����ڂ����L�^����Ă��܂��B
�@2008�N2���ɂ́u�鋫���攪�N�̐��s�v�Œm����A���̐����O�i�ɂ�����E�����݁j����i�ʐ^���j�������̕a�@�ŖS���Ȃ�܂����B���N89�ˁB�����S������`�x�b�g�܂Ŏ����̑��ЂƂŕ����ʂ��A���T�ł̓f�v����m�@�ŏ��V����߁A�C���h�ł͌�H�̕�炵�����ɂ���Ȃǔj�V�r�Ȑt�������A�A������u�l�ԁA�Ō�܂Ŏd���v�ƁA���^�C�A�����ہA�I����łȐl�����т��܂����B
�@�������珺�a�܂ŁA�����҂��͂��߃`�x�b�g�ɓn�������{�l��10�l���܂��B
�@�����̒����A�����̌��T�����߂ė��������\�C���i�̂��݁E�䂽���j�A�͌��d�C�i���킮���E�������j�A���{�U��i�Ă���ƁE���j�A�O���Ȃ̓��ʔC����ттĐ����������c���P�i�Ȃ肽�E�₷�Ă�j��4�l�������Ɂu���O���[�v�v�Ƃ���ƁA�A������������吳�ɂ����ĂQ�x�`�x�b�g���肵���`����Y�A��ێ��Y�i�₶�܁E�₷���낤�j�A��J�����̖��Ń��T�̑m�@�ŏC�s�������c���ρi�����E�Ƃ�����j�A�ؕ����i�������E�Ԃ傤�j��́A�u��Q�O���[�v�v�Ƃ��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
�@���a�̎���ɓ����Ă��炭���{�l�̃`�x�b�g�s���͓r�₦�܂����A�����ƊJ�킵���R���̓`�x�b�g�͂��߁u���k�v�̏�ɊS�������A�����Ƃ��ē��{�̐N�����𑗂荞�����Ƃ��܂����B�쌳�r���A�ؑ��썲���i���ނ�E�Ђ����j�A�����O��́A����������w�i�ɑI�ꂽ�����ł����B
�@�`�x�b�g��ڎw�����ŏ��̓��{�̗��l�̍s������S�N�𐔂���2001�N���A���������u�\�l�͂Ȃ��`�x�b�g���߂��������@�`�x�b�g�Ɠ��{�̕S�N�v�Ƃ����t�H�[���������s���܂����B
�@���̃t�H�[�����ɓ��ʎQ���A�����̒��O�i�Ȃ�ƒ����2�{�̎Q���҂�����܂����j�̑O�Ń`�x�b�g�ł̑N��ȑ̌�������Ă��ꂽ�̂��A�쌳�A���삳��ł����B
�@���̃t�H�[�����ł̂���l�̌����A�������e�́A����Ȉ�ۂ��������Ɏc���܂����B���̋@��ɁA����́A�`�x�b�g���߂�����10�l��U��Ԃ�ƂƂ��ɁA����l��14�N�O�̃t�H�[�����ł̋M�d�ȉf������f�A�ł��邾�������̊F����Ɍ��Ă��炨���A�ƍl���Ă��܂��B
�@���̔��Ȑ푈�̎�����삯��������2�l�ւ̊��ӂƒǓ��̐S�����߂āu������̐��70�N�v�����s���܂��B�ǂ����A���̋@��������Q�����������B
2015�N8��15��
�����O�A�쌳�r��������Â�Ń`�x�b�g�Ɠ��{���l�����
��\�@�]�{�ÐL
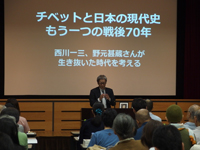 �@ �@
�i�����̗l�q�j
�@�@�@�@�@�@�@�@
|